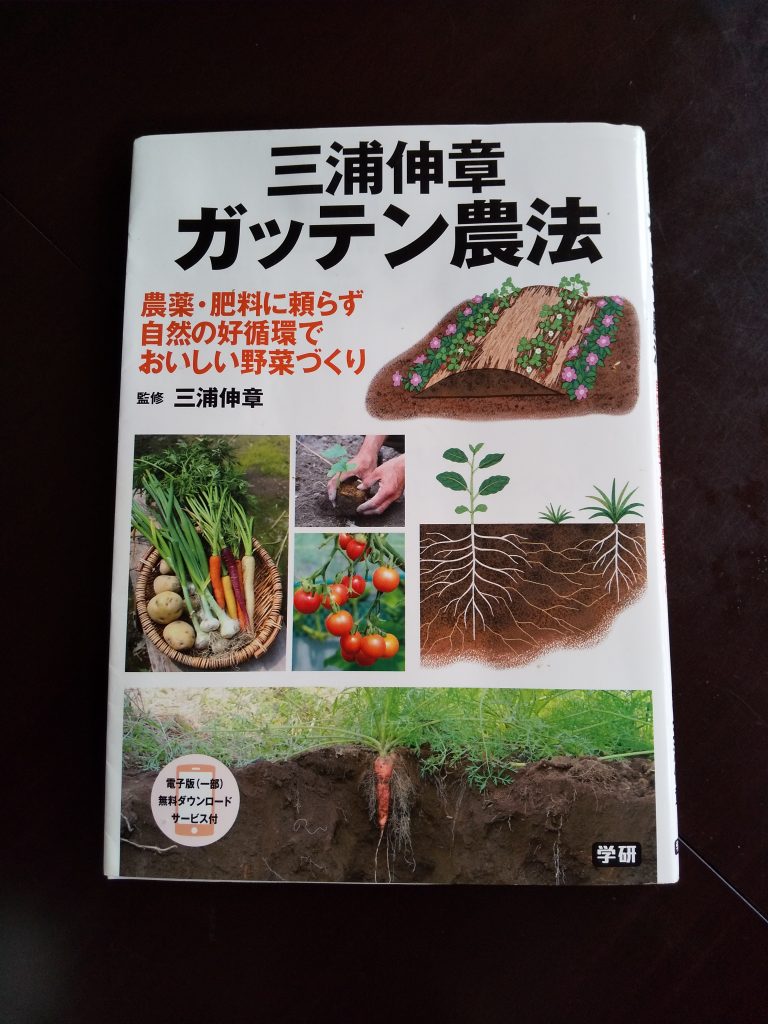本日は町内のテレビ協同組合の定期総会に参加した。テレビ組合って実家の地域には無かったので初めて聞くのだが、テレビを見るに当たっての電柱・ケーブルの管理や維持業務を行うようである。現在ではスマホ・パソコンやBS放送、ひかりTVなどが広がっているが、組合の運営が無ければテレビを見ることは出来ない住民もいるのだ。
組合が組織された当時から比べて現在は1/3戸の住宅が減っており、更にこれからも減っていくだろう事や、かつて住民たちで行っていた電柱回りの草刈りを高齢化などにより業者に頼むようになったりなど、予算がひっ迫しだしている。そこへ、去年暴風による倒木でケーブル線が切断されかかる事態となり、修繕費用が70万かかってしまった。組合の貯金額が大幅に減り、もし今年も同じようなトラブルが発生した場合に立ち行かなくなるため、今年は据え置き、来年度から会費を倍の6000円にしようという提案があった。
事前に値上げの話し合いになる旨の報告はあったのだが、浸透しておらず初めて知る住人が多数おり、話し合いは難航。しかし、現状から致し方ないとの決着がつく。さらに言うならば今後組合員数が激減し維持困難になった場合は解散になろうが、電柱・ケーブルの撤去作業に150万程は用意しておかなければならないのだ。実家のある地域にも、こうした歴史があって現在に至るのかも知れないな。
さて、ざっくばらんな話し合いの場、口調は強くても喧嘩になることはなく、皆言いたい意見を述べ、最後は笑い声で丸く収まる。あまり顔色を窺いすぎることも無く居心地は良好である。今回参加は16世帯。そしてこのところのご時世ネタである。16人中、完全ノーマスクが2人、鼻だしマスクが一人(時々外す)。少し前に国立感染症研究所が新型コロナのエアロゾル感染を認めた。窓は全開、換気は万全。鼻出しマスクの男性が司会者に「聞こえないからマスク取ってよ」と意見。「いやいや、私は…」「気になるなら離れて喋れば良いだろう」などと続いたが結局司会男性はマスクを外さなかった。しかし、着用していないからと言って問題視する人間は誰もいない。こうやって少しづつマスク社会が終焉に向かえば良い。