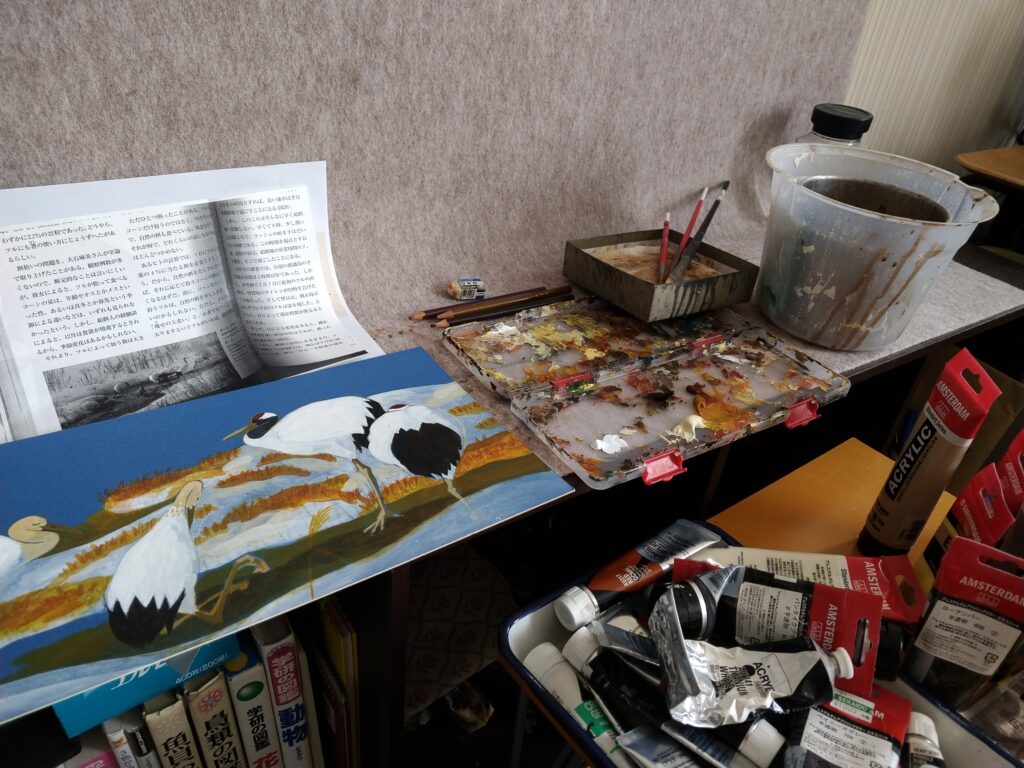父親が彫刻の制作活動の60周年を迎える。4月の末から、本郷新記念札幌彫刻美術館で60周年の記念展を開いていただける事になった。それは後日紹介させて頂くとして、今回は展示準備の作業中の出来事を。
このところ、記念展にむけて準備の手伝いをしに実家へちょくちょく戻っている。数日前は、美術館から要望のあった作品の画像纏めを行っていた。アイコン画像を見ながら、元データをファイリングしていく。風髪’80というタイトルの作品の元画像を見つけて添付したのだが、美術館から届いたアイコン画像とどうも様子が違う。どちらかのタイトルが間違っているのだろうか…と、父に問うと同じじゃないの?と言ってくる。いやいや、そっくりなのだが、肩の切れている場所が違うし、体のひねりも違う。「え~、これ絶対違う作品だよ。」と言うと、「このタイトルの作品は一つしか作ってない、角度が違うから別の作品に見えるのではないか?」と返事がくる。そんなわけないではないか、向かって右の腕が、片方は付け根から、もう片方は少し下あたりで切れている。「これは、同じ時期に同じテーマで2パターン制作したのではないのか?」と聞くと、「そんなことは絶対にない、これは初めてテラコッタで制作した、活動の転機となった記念すべき作品なのだ。」と言ってくる。そうなのだ。おまけになかなか大きくてたいそう重い。背景からも二つ作ったとは考えにくい。
 A
A
 B
B
母親を呼んで画面を見てもらうと、なんとこの作品は曰く付きのものだと言い出した。もう随分前に作品集を出す際に、こちらの作品の撮影をして画像を見ると、頭の上に煙が立ち上っている。これは、大きな埃でも落ちてきたのではないのか? いやいや、このようにはっきりと映っている煙が埃ならば、撮影中に気づくはずだし、撮影後も探せば見つかるはずだ。でも、この煙は画像を見て初めて現れたものなのだ。その時はパソコン上で煙を消して画像を使ったので、元画像は残されてはいない。もしや、今回の作品の変化にこの煙がかかわっているのではないのか。そう、これまで2度記事にした例のマンデラエフェクトである。
しかし、自分の中に仮説があった。家に帰り、自分のパソコンで写真を眺めた。試しに片方を反転させて比べると、方向は違うのだが、同じ作品であることが判明した。何のことは無い、画像が反転して保存されていたのだった。
 A
A
 B 反転
B 反転
しかしである。作品の記録用の写真を反転することなど絶対にありえない。カメラの撮影時、初めから反転の設定があるのかはわからないが、パソコンに取り込むまでの作業の間に、うっかり反転する機会は無いように思える。また、その後もう一つ反転した別の作品の画像が見つかったので、うっかり操作ミスを二つもするようなことがあるだろうかと疑問が残る。この度の騒動のカラクリは、マンデラエフェクトが起こり現実を擦り合わせるようにして、反転したという過去が構築されていったという事なのではなかろうか。う~ん、そう考えなければ、気持ちの落としどころが無い。
なんでマンデラエフェクトがあってほしいかというと、過去にやらかしてしまったあんな事やこんな事が今いる世界線では無かったことになるのではないかという淡い期待のせいなのだった。いや、本当に、無かった事なのかもよ。