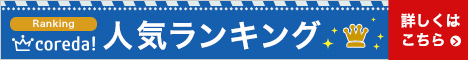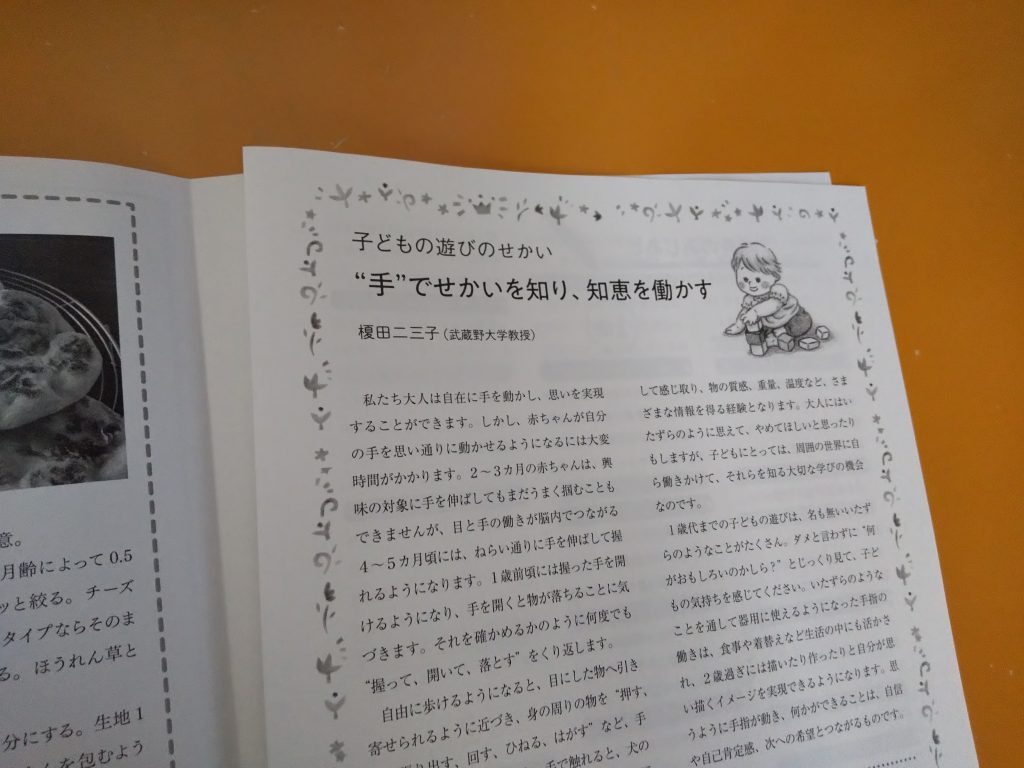塩谷の塩が完成したと仮定して、塩商品を考えていた。その中の一つ、塩アイスはどうか。小樽の中心街と違いこの辺にアイス屋さんはないので、ご近所さんのちょっとした憩いになれば良い。そこで早速、実験的に家庭用アイスメーカーを購入。
アイスクリームやらジェラードをとりあえず付属のレシピ通りに作ってみる。なかなか美味しいぞ。しかし、冷蔵庫で2時間も保管するとすっかりガチガチに固まっている。うーんこれではお客さんが来てすぐに提供することが出来ない。ただ生クリームの分量が多い方が空気の含有量が増えるため多少柔らかい時間の持ちが良いようだ。ちなみに、アイスが溶けだすと含まれていた空気がすぐに抜けていく。手作りアイスは作ったそばからス~っと溶け出すので、すぐに冷凍庫に入れても空気が抜け出した状態だから難しいのかも。
ネットで調べると柔らかさ持続のためにゼラチンを入れる方法があったのだが、舌触りがアイスっぽくなくなってしまう。試しに最近みつけたホットチョコレートをアイスにしたらどうかと考えた。イタリア在住の奥様の動画で紹介されていたのだが、牛乳・ココア・砂糖と、トロミ付けにコーンスターチを入れていた。作ってみたらトロトロだ。生クリームは高いので、生クリーム代わりになるかも知れない。しかし、出来立ては良い具合なのだが、やはりすぐにガチガチに凍ってしまう事は変わらなかった。それに、今時アイスにゼラチンやコーンスターチ入れてるのって売り物としては邪道で敬遠されてしまうかもだな。(*後日コーンスターチについて調べると、有機や無添加にしても製造工程でも色々あるようだ。片栗粉とは随分違うな。)
その後、あまり眼中になかったシャーベットを作るべく、リンゴジュースにシロップ状のオリゴ糖を混ぜてメーカーに投入。舌触りの良いシャーベットが出来た。これもすぐにがちがちになるんだろうな、、と期待していなかった。ところが、そのシャーベットが数日経っても冷凍庫から出したてでスプーンですくえるのだ。びっくりした。ならばとアイスクリームの素材の糖分をシロップ状のオリゴ糖に変えて再制作。しかし結局長時間柔らかくはならなかった。なんでだろーー!
そこで、作ったアイスをグループ分けにして時間差でそれぞれ冷蔵庫に移していき、1時間半が丁度良いのでその時点で冷凍庫に戻し、例えば10分おきにそれぞれを冷蔵庫と冷凍庫を行き来させると考えた。これでいつお客が来てもすぐに提供できるように、…考えたが、そんなことできるか~い!!笑 頭ごちゃごちゃ、パズルみたいになるな。
もういっそ、業務用のアイスメーカーを買おうではないか!!適度な温度で、撹拌し続けている状態で冷やされ柔らかさを保つことが出来る。探してみると、50万前後~130万などというものもある。ところでウチをアイス屋さんにして一日何人ご近所さんくるかなあ~、一日5人位かな。。(遠い目)。アイスはやっぱ、自分で食べるに限るかもね!
 結局お気に入りのmyアイスメーカー♪
結局お気に入りのmyアイスメーカー♪