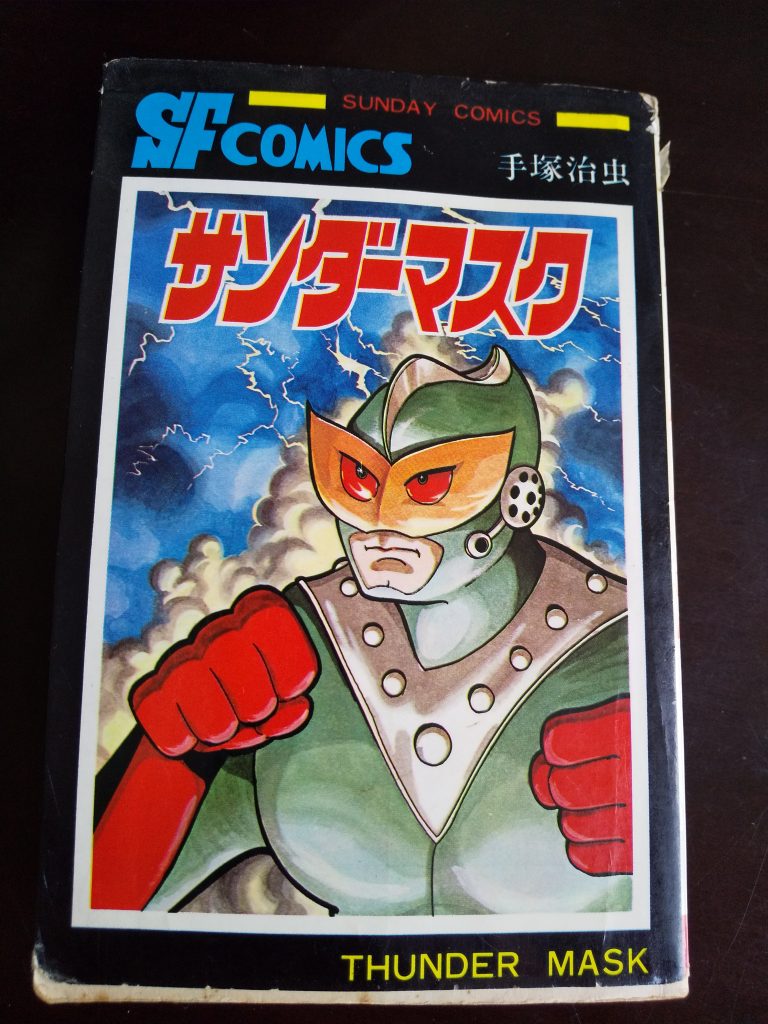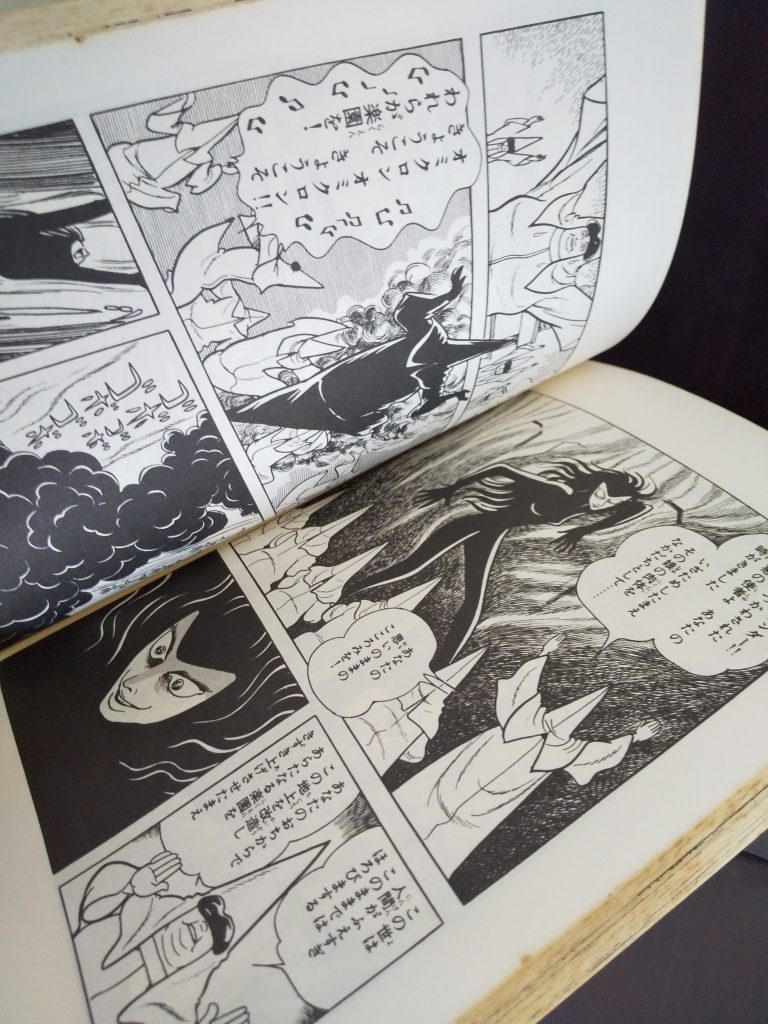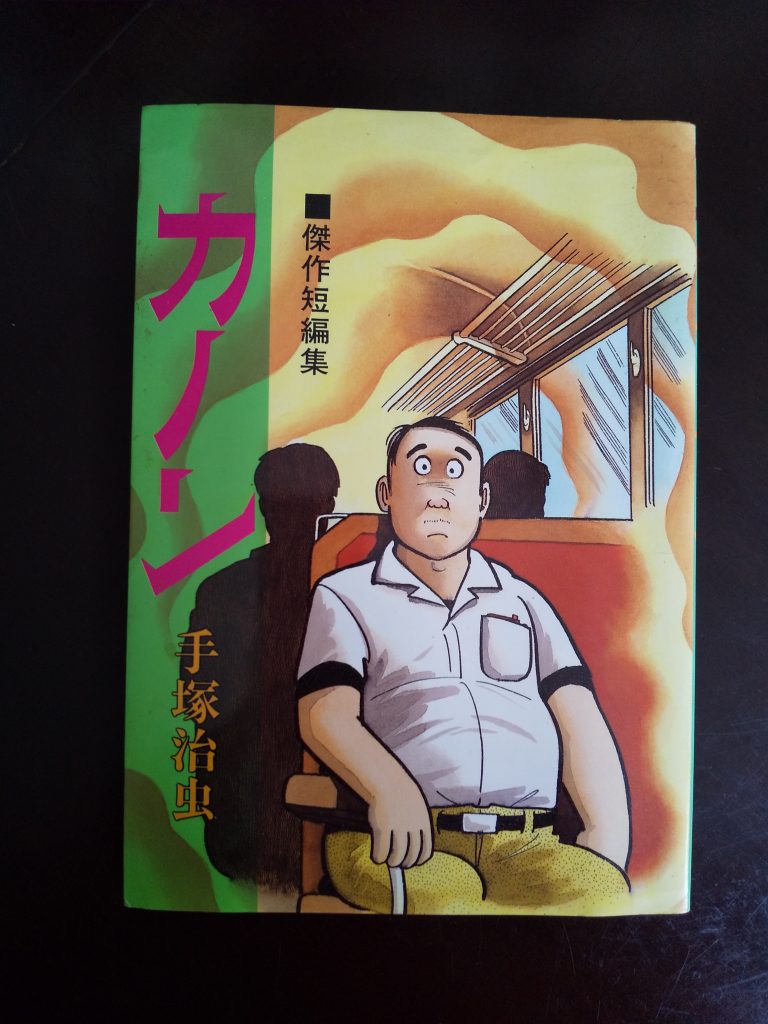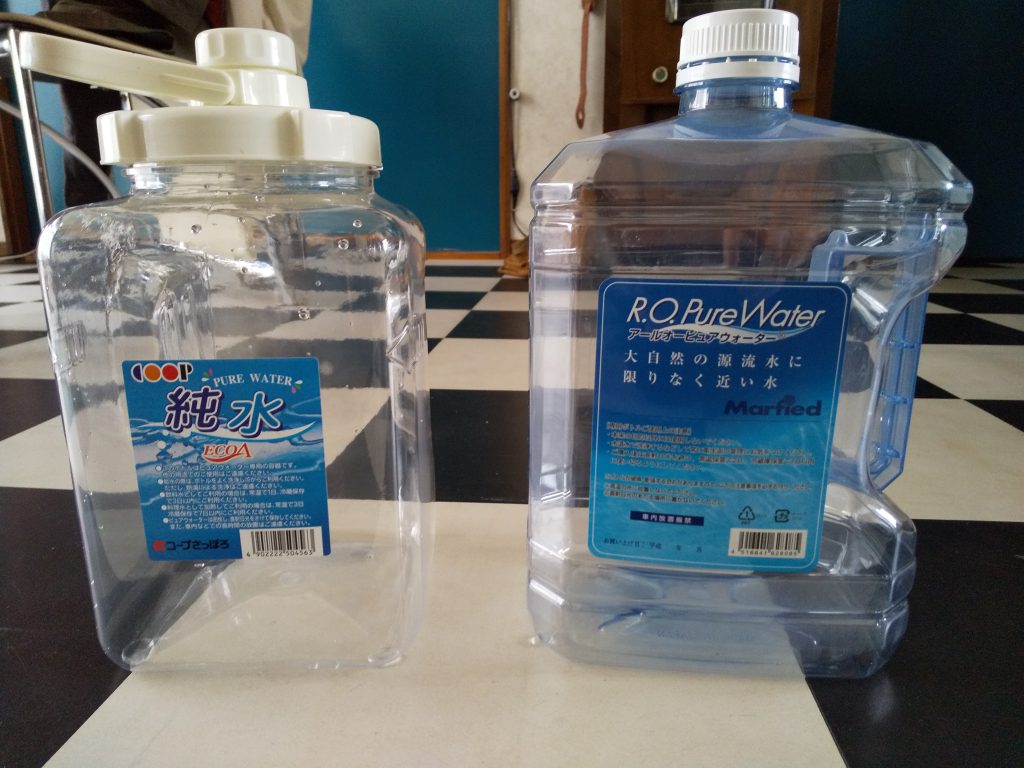高校時代の美術部の先輩、秋山一郎氏。高校生の頃は洋画を制作しておられたが、大学に進学し道外に出てから立体も手掛けるようになっていった。そして2019年、小樽美術館の企画展・鈴木吾郎と新鋭作家展でご一緒した。作品は日常で使用する木工のスプーンやクルミなど様々な植物で染められた布物や和紙、更にはアクセサリー、染めた布で作ったエプロンやら、果てはパイプオルガンまで。実生活では家の改築は全て手掛け、階段制作が大変だったり、家で使うものは何でもかんでも手作りしているようなのだ。
「昔ながらの技術でつくられたそれらの作品は街中でもよく見かけられるものですし、作品としての独創性を追求し人を驚かせたりする要素があまりないかもしれません。しかし、四季を追いかけて身近な自然物を相手にしながら私は、私の制作と私がいきているという事とが、今になってはじめて一致してきたように感じています。」 展示期間中のイベントのチラシの言葉を抜粋
う~んこれこれ!最近の私たちの営む生活でこういうことにつくづく共感。いや、私たちはまだお遊び程度なんですが。展示で、壁一面にズラッと飾られた木工スプーンは圧巻。ある時左手用のスプーンを依頼され、ジャストフィットする形を求めてあれこれ制作を重ねていくうちにこのような情景になっていったようだ。こうして展示されるとやっぱり現代アートだな。
ああ…手元に画像が見当たらない。実家だな。。ということで散歩日記Xというブログで紹介されているのでリンクを貼っておきます。小旅行(4)という記事です。もう一つ、小樽ジャーナルより
期間中行われたパフォーマンスのチラシ。かろうじてパイプオルガンが写っておる。⇒
 オルガン演奏は高校の同期で音楽家の秋山洋子氏
オルガン演奏は高校の同期で音楽家の秋山洋子氏
「今回の作品は現物にこだわりました。例えば草木染の布にはとてもきれいな色が出るけれども、これを写真に撮っても、この綺麗な色はなかなか写らないです。 明日はパフォーマンスとしてスプーンを使った実食を行います。スプーンは口で感じるものです。~中略~パイプオルガンも生音です。作った5年前から家にあって、子どもがいじっていても、決して飽きることがない。その場でしか味わえない本物の魅力を感じて頂ければ嬉しい。~中略~こんなに豊かな質感の世界があったのだということを、感じていただけたらと思っています。」アーティストトークの文字起こしより抜粋
現在畑使用の土地は購入時笹薮であった。笹はいくらでも手に入るので、今年は笹の葉で何かできないかと目論んでいる。